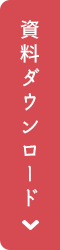第33回 経営者コラム|トレンドについて考える#01 レトロと未来の共存。「デジタル疲れを吹き⾶ばす?」【電動モビリティ】で⾵を切って進もう!

⽇経トレンディ2025年ヒット予測ランキングでは、
「電動モペットや格安バイク」が上位にランクインし、
「電動モペット・電動バイク・、キックボード」など
【電動モビリティ】の注⽬が⾸都圏から地⽅にも広がってきました。
※Mobility(モビリティ)は直訳すると、移動性・可能性という意味
そんな中、そのデザインやその使い⼼地が、
どことなく宮崎駿監督のアニメに登場する乗り物にリンクする
と感じる筆者は、古い感覚と新しいものの融合=レトロと近未来の融合が、
少しずつ始まっていると感じずにはいられません。
今回のコラムは、デジタル疲れを抱える現代⼈にとって、
2025年に⽣産が終了する50ccバイクの背景や代替⼿段として台頭している
電動バイクや電動モペットが新しいライフスタイルの移動⼿段として
⾝近な存在となりつつあることを念頭に、
ガソリンなどのエネルギーを使⽤しないことをレトロと位置付け
中⼩企業や事業者の【電動モビリティ】の活⽤の可能性について触れていきます。
目次
⽣産廃⽌となる50cc バイク。台頭するのは未来的レトロな乗り物
2025年をもって50ccバイクの⽣産が終了する理由、
それは、SDGsにも関わる環境規制の強化にあります。
⼆酸化炭素排出量を抑えるため、エンジンを使⽤する⾞に代わる
電動⾞両への移⾏が求められています。
また、若者のバイク離れも影響しています。
近年、都市部でのバイク需要が減少し、維持費や駐⾞場問題なども
敬遠される要因となっています。
さらに、⾼齢化社会へと進んでいく中、運転免許の⾃主返納者が
増えていることも市場縮⼩につながっていると思われます。
コラム内では、[近未来レトロ=電動]という価値観で考えていきますが、
ガソリンを使⽤しない電動⾞両は環境に優しく、
近未来的なデザインを持ちながらも、どこか懐かしいレトロな要素、
例えば、「⾵を感じられる」「⼈との距離感が近い」などの感覚が、
昭和レトロブームと未来志向のライフスタイルが⾒事に調和した
新しい選択肢が広がっているように思えてなりません。
こうしたミックススタイルの乗り物は、今後の予想として、
若者から⾼齢者まで幅広い世代に⽀持され、
トレンドの中⼼を担う存在となりつつあるのです。
電動バイク、電動モペットなどが⽇経トレンド2025で、9位に!
⽇経トレンディの2025年ヒット予測ランキングでは、
【電動バイクが第9位】にランクインしています。
具体的な製品として、Glafit社の「電動バイク GFR-02モビチェン付」や、
YADEA社の電動スクーター「Modern(モダン)」が挙げられます。
これらの製品は、環境への配慮や利便性から注⽬を集め、
2025年の主要トレンドとして期待されています。

画像出典: Glafit, ⽇経トレンディ「2025 年ヒット予測」ベスト30 に2 製品受賞の快挙。
「電動バイク GFR-02 モビチェン付」第9 位、「四輪型特定⼩型原動機付⾃転⾞」第28 位にそれぞれランクイン!
,https://glafit.com/news/news20241101/

(画像出典:glafit,https://glafit.com/products/gfr/gfr-02/)
それでは、「各電動モビリティ」の違いや特⾊を⾒ていきましょう。
・電動バイクとは?

(画像出典https://www.youtube.com/watch?v=GiOFiRx_jjAYoutube、/XEAM EVch【全5⾞種】⼈気の電動バイク)
電動バイクは、ガソリンエンジンの代わりに電動モーターを搭載した⼆輪⾞です。
最⼤の特徴は、静⾳性と環境への配慮が挙げられます。
また、充電ステーションの普及が進む中、⻑距離移動にも適したモデルが
登場しています。
利⽤者層としては、通勤通学やアウトドアを楽しむ若者、
そして環境に配慮したライフスタイルを重視する⼈々が挙げられます。
・電動モペットとは?

画像出典:バイク!といえばグーバイク,電動モペット(フル電動⾃転⾞)を
バイク販売店で購⼊するメリット,https://www.goobike.com/electricmoped/
電動モペットは、⾃転⾞とバイクの中間的存在で、
ペダルと電動アシストを併⽤可能な乗り物です。
短距離移動や通勤通学に適し、特に若者や⾼齢者に⼈気です。
軽量で⼩回りが利くため、都市部での活⽤が広がっています。
シンプルな操作性が特徴で、⾼齢者にも使いやすい点が評価されています。
・キックボードとは?

画像出典:バイク!といえばグーバイク,電動キックボードをバイク販売店で購⼊するメリット,
https://www.goobike.com/electrickickboard/
電動キックボードは、⽴ち乗りスタイルの乗り物です。
特に観光地や商業施設内での利⽤が拡⼤中です。
⼀部⾃治体では公道⾛⾏が許可され、通勤⽤途でも注⽬されています。
その軽快さから、若者や観光客に⽀持されていますが、
少し体幹が必要かもしれません。
・それ以外の似た商品との違い
ほかにも似た商品として「電動スクーター」や「シニアカー」があります。
電動スクーターはデザイン性に優れていることから「若者向けの商品が多い」⼀⽅、
シニアカーは「⾼齢者の⽣活をサポートする⽤途に特化」しています。
【電動モビリティ】
電動モビリティとは、電動モーターで動くすべての乗り物を指します。
【⼩型モビリティ】
電動モビリティの中に⼩型モビリティのカテゴリがあり、電動スクーター、電動キックボード、モペット、電動アシスト⾃転⾞、シニアカーなどが、⼩型モビリティです。
出典:PAI-R, 超⼩型モビリティ・電動モビリティの種類⼀覧を紹介|法律を理解し正しく運⽤するために,
https://pai-r.com/column/20241125/.2024.11.25

画像出典:国⼟交通省,現⾏制度について,
https://www.mlit.go.jp/common/001430302.pdf#page=2
中⼩企業や事業者にとっては、今後、これらのさまざまな電動モビリティを
活⽤した商品展開やサービス開発の可能性が感じられます。
免許の必要有無は?価格帯はどうなのか?
電動バイクや電動モペットの中には、排気量に応じて原付免許や
普通⾃動⾞免許が必要なものがあります。
反対に、電動キックボードや⼀部の電動モペットは免許不要なモデルも存在します。
プライベートでも企業活動としても「免許の必要不要」をきちんと調べた上で
活⽤することが前提条件となりますので、注意が必要です。
おおまかな価格帯は以下の通りです
• 電動バイク:20〜50万円
• 電動モペット:10〜30万円
• 電動キックボード:5〜20万円
各製品の購⼊時には、充電設備やメンテナンス費⽤の加算が必要な
場合もありますのでこちらも注意が必要です。


出典:バイク!といえばグーバイク,電動モペット(フル電動⾃転⾞)をバイク販売店で購⼊するメリット,
https://www.goobike.com/electricmoped/
企業がこれらの電動モビリティを活⽤する際には、
コストと効果のバランス、そして、前述の免許の必要有無の確認が重要です。
「⾼齢者利⽤」と「交通ルール」。⾸都圏と地⽅都市での活⽤の⾏⽅
免許を返納した⾼齢者にとって、電動モペットやシニアカーは
⽣活の質を向上させる可能性がありますが、
交通法規の点から⾒ると、免許が必要な電動⾞両を
無許可で利⽤するケースや、交通ルールを守らない事例も報告されており、
報道でも取り上げられています(出典:Mainichi)。
こうした問題への対策として、利⽤者への教育や厳格な規制が求められています。
また、これらの課題を解決するために、
中⼩企業や事業者などが⾼齢者向けサービスや教育プログラムを提供することも
可能ですし、⼀つのビジネスモデルになり得ると考えます。
⾸都圏では、都市部の混雑した交通環境にその機動⼒が評価され
電動モビリティはすでに多くの⼈々に利⽤されています。
地⽅都市ではこれからのさらなる拡⼤として、
公共交通機関が乏しい地域や、通勤・通学や買い物など、
⾝近な移動⼿段として電動モビリティの活⽤が期待されています。
中⼩企業においても、地⽅特有のニーズに応じたレンタルサービスや
出張メンテナンスといったビジネス展開もできるでしょう。
まとめ
デジタル疲れというワードを度々⽬にする機会が増えました。
外へ出かけることはデジタルから少し離れる良い機会でもあります。
外出⼿段として活⽤する「電動バイク」や「電動モペット」など
のモビリティは、環境への配慮だけでなく使いやすさやデザイン性も⽀持され、
過去と未来を繋ぐこれらの乗り物が2025年以降のトレンドの⼀つとなること、
そして、⾝近なものになることは間違いありません。
中⼩企業や事業者にとっても、これらの電動モビリティを活⽤した
新たなビジネスチャンスを⾒逃してはいけません。
本⽂中で述べた「電動モビリティのレンタルサービス」
「地⽅観光地での移動⼿段の提供」「地域特化型のカスタマイズ」や
「販売サービスなど」の取り組みにより、地⽅都市の活性化や
新たな雇⽤創出にも貢献できそうな予感です。
でもその際は、仕様の注意、メンテナンス、免許の有無など、
熟考の上、取り⼊れることを、くれぐれもお忘れなく。
【注意点!】
多くのモビリティが⽣まれたことにより、種類が多岐に渡りすぎ
利⽤する私たちも混乱し、法整備も追いついていない状況です。
注意点として、同じ電動モビリティでも
「道路交通法」と「道路運送⾞両法」では⾞両区分が異なるため、
⼈によって電動モビリティの交通規則があいまいな捉え⽅であるケースが
多いことが、利⽤時の懸念点となっています。
⾮常にわかりづらいため、電動モビリティに乗ったり、事業利⽤したりする際は、
使⽤する⾞両の道路交通法と、道路運送⾞両法で定められた規則を、
必ず確認するようにしてください。
各モビリティによって、免許やナンバープレートの取得などが必要な場合や、
規則を守らない場合は罰則の対象になります。
楽しく快適に乗り利⽤するために、現状では、事前確認が必須ですが、
SDGsにも配慮した環境に配慮した⼿軽な乗り物である
【電動モビリティ】を楽しみながら使いこなすため、近い将来、
分かりやすい法整備となることに期待します。
出典:PAI-R, 超⼩型モビリティ・電動モビリティの種類⼀覧を紹介|法律を理解し正しく運⽤するために,
https://pai-r.com/column/20241125/.2024.11.25