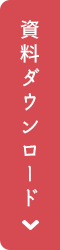第41回経営者コラム|トレンドについて考える09 ノマドワーカー受け入れ地域 「ノマド村(町)」がもたらす 地方ビジネスの可能性!!

ビジネスの世界でいう「ノマド」とは、特定のオフィスに縛られず、
パソコンとインターネット環境さえあれば世界のどこでも働ける人を指します。
観光客が短期で消費して去るのに対し、ノマドは数週間から数か月にわたり地域に根を下ろすため、家賃や食費、交通費といった生活支出を地元に落としやすいのが特徴です。
その存在は、観光需要の季節変動に左右されにくい安定収益をもたらし、同時に新しい交流や雇用の芽を生み出します。
広島市に本社を置くみらい(株)は、全国にサテライト拠点を設け、登録者のスキルを活かせる仕事の場を提供しています。
熊本県天草市の「あまスタ★ファロール」もその一例で、在宅やオンラインを中心に就労機会を広げる仕組みです。育児や介護で働く時間に制約がある人にも門戸を開き、登録者は自宅からオンラインで業務を行ったり、
拠点を「自分のオフィス」として活用したりできます。
さらに海外在住者や留学経験者、国内外を行き来する人々、
いわゆる「ノマド」層も参加し、多様な働き手が地域とつながっています。
このように、地方にいながら都市や海外と仕事を結ぶ事例は、地域に新たな雇用と
交流をもたらし、都市との関係性を変えていく可能性を秘めています。
ここから先は、海外で広がる「ノマド村」の動向と国内の最新事例を重ね合わせ、地方ビジネスの未来を考えていきます。
出典:内閣官房まち・ひと・しごと創生本部,“地方創生テレワーク推進企業(みらい株式会社)”,内閣官房まち・ひと・しごと創生本部,2023-09-20,https://www.chisou.go.jp/chitele/sengen/company/312.html,2023-09-20
目次
海外で広がる「ノマド村」ブーム
―――本当にビジネスにつながるのか?
バリ島やポルトガル・リスボン、ルーマニア、ジョージアなど、
東欧やコーカサス地域では、ノマドワーカーを受け入れる「ノマド村」が
広がっています。これらは自然豊かな土地や歴史ある都市を拠点に、
宿泊とコワーキング(*1)を一体化した仕組みを提供し、
地域の飲食・交通・観光産業に効果をもたらしています。
(*1)コワーキングとは=「共同」を意味する「Co」と「働く」を意味する「working」を組み合わせた造語で、
多様な職種の人が一つの空間を共有しながら、それぞれ独立して働くスタイルを指します。
◎リスボンでは、
温暖な気候とEU圏内での働きやすさを背景に、
カフェやコワーキングが地域経済の一部として根付き始めています。

Co.Lisbonは改装された4階建ての施設で、28の個室やスタジオを備え、1階には共用ラウンジやコワークスペース、
庭を設け、快適な住環境と交流拠点を提供しています。(参考:https://colisbon.com/)
【EU圏内で働きやすい理由】
1.多くのEU加盟国がシェンゲン協定により、国境を越えた移動が容易
2.ユーロの使用により為替リスクや両替の負担が軽減
3.労働条件や社会保障の共通基準により制度がわかりやすい
4.高速通信・交通網・医療水準が比較的整っている
◎バリ島では
「暮らし+仕事」を一体化した施設が国際的に注目を集めています。

Luxury Traditional Villas w/ Coworking + Pool + Gardens(バリ・ウブド)。ヴィラタイプのコリビングで、コワーキング設備や共有ラウンジ、プールなどを備え、暮らしと仕事を同時に支える拠点となっています。
画像元URL:https://coliving.com/spaces/7eq4qcbw
【バリ島・ウブドの実例】
代表例として、Luxury Traditional Villas(ウブド)はヴィラタイプのコリビングで、
コワーキング設備や共有ラウンジ、プールを備え、生活と仕事を両立できる拠点と
なっています。また、Outpost Ubudは宿泊・コワーキング・交流を兼ね備えた施設で、多国籍の利用者が集う拠点として知られています。
周辺にはカフェ一体型のコワーキングや小規模コリビングも点在し、
長期滞在者が「暮らしと仕事」を両立できる環境が形成されつつあります。
つまり
これらは「観光施設+仕事場」ではなく、
“暮らしの場+働く場+交流の場”を兼ね備えた新しい拠点といえます。
地域にとって安定収益につながる
可能性を持つ存在「ノマド」
光庁の調査(*2)によれば訪日外国人旅行者は1回あたり平均約6.9日で
約22.3万円を消費するのに対し、デジタルノマドは1か月で約36.0万円を
支出しています。滞在日数が長いため、地域にとっては持続的な収益源と
なる可能性が高いといえます。
(*2)調査資料:観光庁,“国際的なリモートワーカー(デジタルノマド)に関する調査報告書
”,観光庁,2024-03-31,https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001891364.pdf,2024-03-31,

環境省本省が入る中央合同庁舎第5号館の外観
画像元:環境省,“環境省本省庁舎の写真(外観)”,環境省,更新日不明,https://www.env.go.jp/content/900490120.jpg,
地方が海外の好事例を参考にする際には、通信・住宅・生活インフラを整備し、
平日型の需要を支える工夫が欠かせません。
取り入れやすい事例
空き家を「家具付き短期賃貸+コワーキング」に転用し、料金にWi-Fi、光熱費など
を含める。観光客ではなく“暮らす人”を意識した料金設計にすれば、
安定収益と地域消費を生む基盤になりやすいと考えられます。
日本でも和歌山・熊野・香川でノマド実証が前進(熊本でも動き)
国内でも和歌山県、熊野古道、香川県琴平町などでノマド誘致の
実証事業が進んでいます。和歌山は公式ワーケーションサイトを刷新、
熊野古道では文化財建築を活かした滞在プラン、琴平では宿泊とコワーキングを
組み合わせた「コトリ コワーキング&ホステル」が注目されています。
海外に目を向ければ、スペインやイタリアの田舎町でも「歴史的建物×ノマド誘致」
の事例が生まれています。これらは、熊野古道や琴平の取り組みと共通点が多く、
日本の地域でも応用できる事例が見受けられます。


宿泊と仕事を両立できる木の温もりある空間
画像元:WORK MILL,“香川県高松市に「コトリ コワーキング&ホステル 高松」…”,WORK MILL,2023-08-18,
https://workmill.jp/jp/webzine/kotori-20230818,2023-08-18
海外のスペインやイタリアでは、修道院や古城をリノベーションした
ノマド誘致が進んでおり、「歴史的建物の活用」「暮らし型観光への転換」
「地域消費の波及」「住民交流」という点で日本の事例と共通しています。
ノマド層が求める
“暮らせる観光地”とは?
ノマド層が求めているのは、一時的な観光体験ではなく
「暮らすように滞在できる場所」 です。
その条件は大きく5つに整理できます。
1. 安定した高速通信
仕事の生命線であり、安心して働けるインフラ
2. 1〜3か月滞在可能な住まい
家具付き賃貸やゲストハウスなど中期滞在に適した住環境
3.医療や英語対応
外国人も安心して暮らせる体制
4.交流イベントや文化体験
地域とつながれる仕掛けが、滞在の価値を高める
5. 生活導線のわかりやすさ
交通・買い物・役所手続きなどの不安を減らす

チェンマイの旧市街長い歴史を持つソーダボトル工場をリノベーションしてワーキングスペースに
画像出典:アメージングタイランド観光スポット,パンスペース・ウィアンケーオ,https://www.thailandtravel.or.jp/punspacewiangkaew/
九州は温泉や食文化、生活費の安さで有利。海外でもタイ・チェンマイやスペイン・バレンシアが「暮らせる都市」として選ばれ、地域経済に直結しています。
観光庁の調査では、ノマドの平均滞在日数は100日以上。観光客よりも生活支出が大きく、「暮らせる観光地」としての整備は地方にとって重要な基盤となります。
参考文献:観光庁,“国際的なリモートワーカー(デジタルノマド)に関する調査報告書”,観光庁,2025-09-09,https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001891364.pdf,2024-?(資料記載に準ずる), 国土交通省
参考文献:和歌山県,“わかやまWorkation Project(公式サイト)”,わかやまWorkation,2025-09-09,https://wakayama-workation.jp/,更新日不明, わかやまワーケーション
取り入れやすい事例
商工会と医療機関で「長期滞在者向け生活ガイド」を1ページに集約。
病院の受付時間、英語対応、月額賃貸の窓口、SIM販売、地域イベント予定を
“地図つき”で掲載し、到着初日に迷わせない工夫をする。
地方の空き家・旧校舎・温泉地を活用した
コワーキング×観光戦略のヒント
全国で空き家は増加傾向にあり、総務省統計局の最新調査(令和5年速報値)でも
空き家率が13.8%と過去最高を記録しました。
こうした遊休資産をリノベーションし、温泉地や観光地に小規模な拠点として
配置すれば、平日の利用を促進し、地域の稼働率を高めることができます。
日本では文部科学省の「みんなの廃校プロジェクト」により、旧校舎を再活用する
取り組みが各地で進められています。
海外でもポルトガルやギリシャでは、修道院や歴史的建築をホテルや
ワーケーション施設に改装する事例があり、国内での活用のヒントになります。
また、温泉地・別府市では、市と民間が連携し「宿泊+働く場+体験」を
組み合わせたワーケーションのモデルづくりを進め、注目を集めています。

文部省,~未来につなごう~「みんなの廃校」プロジェクト,
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/1296809.htm
,20250919アクセス
出典:HOME`SBusuness,空き家が前回調査から51万戸増加。空き家率は13.8%と過去最高を更新,https://biz.homes.jp/column/topics-00124#,20240412
出典:文部科学省,“「みんなの廃校」プロジェクト,
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/1296809.htm,20250919アクセス
取り入れやすい事例
旧公民館の一室をコワーキング、隣を地域食堂にする。
利用者は昼に地元料理を食べ、夜は温泉に入る。
小さな循環をつくれば、観光と暮らしを両立できます。
まとめ
“ノマド村”の本質は、箱ものではなく「暮らしと仕事を面で支える仕組み」です。
長期滞在者は観光客と違い、平日・生活支出が地域に落ちる人たち。
だからこそ、地方の事業者にとっては、閑散期の底上げ・新サービスの試行・外部人材との連携に直結します。
デジタル化が進む今、ビジネスはますますデジタルで効率化されていく一方で、
暮らしにおいては「心の平安」や「人と人のつながり」といった
アナログな価値が求められるようになっています。
ノマドの受け入れは、その両方を満たす試みとも言えます。
町の中にできた小さな拠点が少しずつ繋がり、
働きやすく、過ごしやすいエリアや地域になって行き、
点が繋がり、線になり、面へと広がって行きます。
そうなれば、地元の若者や日本人の移住者、海外からの移住者など
いろいろなバックボーンを持った人たちが集うことができ
「観光にやって来るだけでなく、暮らせる場所」=“ノマド村”へと育ち
地方ビジネスの広がり!という可能性のひとつになっていくのです。
日本は島国であり、長く鎖国を経てきた歴史を持ち、
ひとつの民族としての色合いがとても強い国でした。
しかし近年、ハーフやクォーターといった多様な背景を持つ人々が
芸術、スポーツ、ビジネス、芸能界などあらゆる分野で活躍し始めています。
そして、社会全体も少しずつ変化を受け入れる素地が整ってきました。
他地域からの日本人移住者はもちろん、海外からなど
外からの人材や文化を恐れず迎え入れ、本当の意味での国際化を進めることがこれからの日本に必要なってくるのかもしれません。
そして、国際化によって日本文化の素晴らしさなど新たな発見もあるかもしれません。
それは、当たり前のことと捉えていた「日本文化の上質さ」や「日本の日常の素晴らしさ」を、実感するきっかけになるかもしれませんし、
さらには、日本のことがもっと誇らしくなるかもしれません。
“ノマド村”をきっかけに、新たな思考へと踏み出すチャンスが
もしかしたら、訪れるのかもしれません。