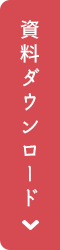第40回経営者コラム|トレンドについて考える08 サステナブルはもう当たり前! 中小・事業者のサステイナブル 消費者への伝え方

今や「エコ」ではなく「サステナブル(持続可能)」が求められる時代です。
世界では、小規模な会社も環境や社会に配慮した経営で注目されています。
例えば、オーストラリアの「The Very Good Bra (*1) 」は、
乳がん経験者が設立した下着ブランドで、プラスチックを一切使わず、
植物由来素材で作られた循環可能なブラジャーを展開し廃棄ゼロを目指しています。
しかし、日本ではまだまだ動きが遅れている印象もあります。
では、中小規模の事業者だからこそできる持続可能な取り組みとは?
大切なのは「大きなこと」ではなく、日々の業務で無理なく続けられる工夫です。
日本人のうち約8割(*2)は、サステナブルな製品に対してプレミアム価格を
受け入れる一方で、実際の購買行動にはつながりにくいという傾向があります。
これは、「何がサステナブルなのかが分かりにくい」ことが、
行動の足かせになっていると言われています。
本コラムでは、中小規模の事業者だからこそできる、
お客様や地域に効果的にサステナブルを伝える方法を、国内外の事例を交えて解説し、
消費者への伝え方について考えていきます。
(*1) The Guardian “A more circular bra: how Stephanie Devine turned an underwear gap into business success”. The Guardian. 2024-12-16. URL: https://www.theguardian.com/paypal-working-capital/2024/dec/16/a-more-circular-bra-how-stephanie-devine-turned-an-underwear-gap-into-business-success
出典(*2)約8割について: Bain & Company Japan.“日本とアジア太平洋地域における消費者のサステイナブル意識”. Bain & Company. 2022-09-29. https://www.bain.com/ja/insights/japan-esg-report-2022/
目次
「サスティナブル=環境への配慮」は
ただ取り組むだけでは足りない。
「どう伝えるか?」「明確に伝えること」が、カギ
サステナビリティへの取組みは実行するだけでなく「どう伝えるか」が
成功の分かれ目。
中小企業向けに作られた「サステナビリティ経営実践ガイド」では、
段階的な進め方や事例が整理されています。
重要なのは、数字や成果を明確に見せること。
「この取り組みでCO₂削減〇〇kg/年」などを表示すれば、
顧客に具体的なイメージを与えられます。
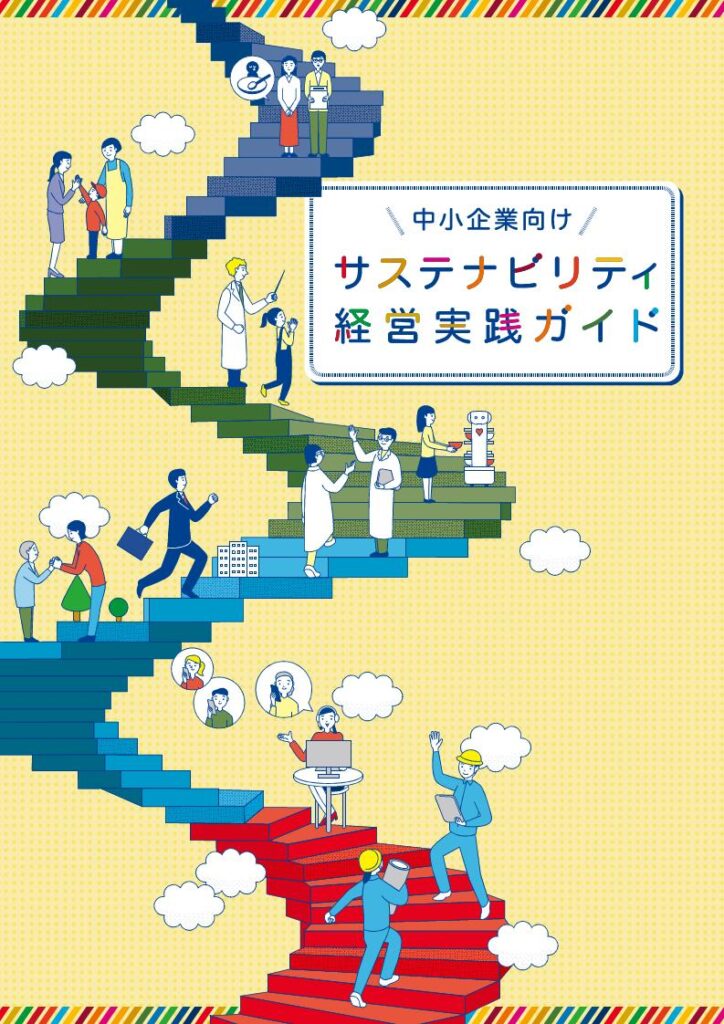
「中小企業向け サステナビリティ経営実践ガイド」
出典(画像含):“サステナビリティ経営実践ガイド”. 大同生命保険. 2024-11-15. https://www.daido-life.co.jp/sustainability/management/practiceguide.html
出典:“非上場・中堅中小企業向けサステナビリティ情報の活用ハンドブック”. SDSC. 2025-06-09. https://www.enegaeru.com/sustainabilityforsmb-guidebook
取り入れやすい具体例としては、店舗で「地元の廃材を使ったリサイクル雑貨」と
掲示し、購入者には次回使用可能なクーポンを提供。
環境配慮への共感とリピーター獲得につながります。
「使い捨てを減らす」工夫や、
「地元素材の活用」をPRに!
前述の具体例のように包装の簡素化や「簡易包装を選べます」という案内は、
顧客にわかりやすいサスティナブルな活動です。
例えば、地元の素材や再利用品を使った製品には、
「地元の自然と共につくりました」と加えると、より親近感が増します。
包装資材メーカーが生分解性素材に切り替えた事例では、
環境意識の高い顧客層からの受注が増加し、売上も伸びました。
 サステナブルパッケージの具体例=木やパルプ素材を使ったテイクアウト容器
サステナブルパッケージの具体例=木やパルプ素材を使ったテイクアウト容器
 地元素材の活用事例=伝統工芸「駿河竹千筋細工」で作られた竹のティッシュケースと竹100%ティッシュペーパー
地元素材の活用事例=伝統工芸「駿河竹千筋細工」で作られた竹のティッシュケースと竹100%ティッシュペーパー
出典: “簡易包装選択など、できることから始めるサステナブル取り組み方法”.
itsumo365. 2022-10-25. https://itsumo365.co.jp/blog/post-17486
出典: “包装資材メーカーの大変革:サステナビリティを経営に活かす成功事例”. Luft-HD. 2025-03-21.
https://luft-hd.co.jp/blog/905
実際例として、地元の間伐材で作ったコースターを
「長く使えて地元の森を守る一品です」とPOPで紹介した事業者では、贈答需要にもつながりました。
小さな取り組みも
意味あるアピールに変える「コピー術」
小さな取り組みでも、伝え方次第で大きな価値になります。
「再生紙を使っています」ではなく「地球にちょっと優しい紙です」と
するだけで印象が柔らかくなります。
サステナビリティレポートも、数字とともにエピソードを添えることで
読者の共感を得られます。
さらに、コピーの決め手は「自分ゴト(*3)」にすること。
(*3)「自分ゴト」とは=環境や社会の問題を“自分には関係ない”と思うのではなく、
「自分の生活にも影響がある」と感じて、自分の行動で変えられることとして考えること
具体例を挙げてみます。
【自分ゴト販促コピー例】
1.△地元産の野菜を選ぼう→
◎「この一皿で、あなたの街の農家を応援できる!」
2.△マイボトル持参→
◎「マイボトル。ゴミも出費もカットできます」
3.△節電で光熱費削減しよう→
◎「省エネはお財布にも地球にもやさしい、チリつも習慣」
4.△節電で光熱費削減しよう→
◎「省エネはお財布にも地球にもやさしい、チリつも習慣」
5.△地元の伝統工芸品を購入しよう→
◎「一生モノの器が、将来あなたの宝に。職人の技術継承をまもろう」
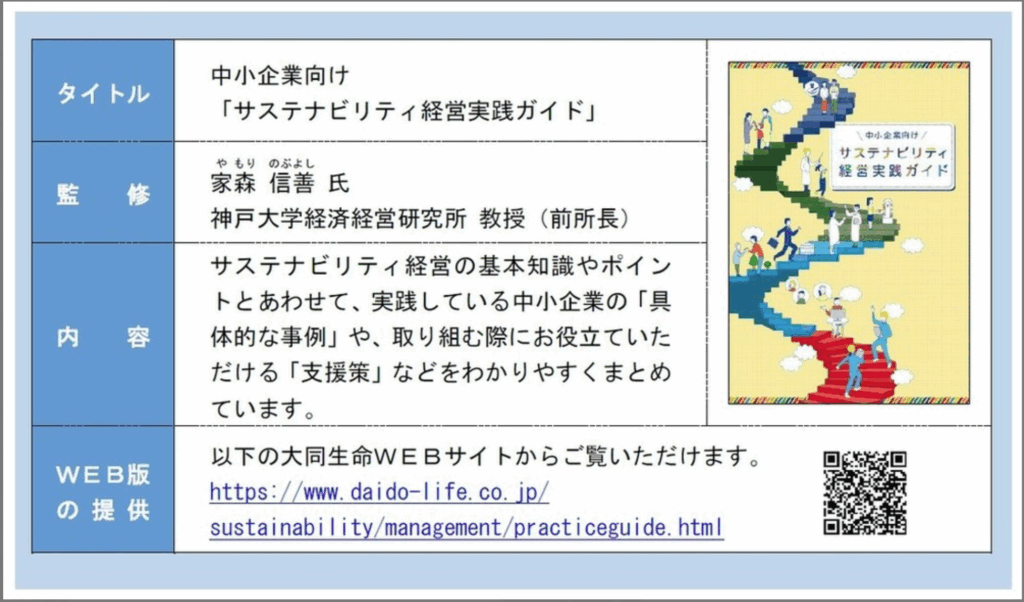 「サステナビリティ経営実践ガイド」
「サステナビリティ経営実践ガイド」
出典(画像含):“サステナビリティ経営実践ガイド”. 大同生命保険. 2024-11-15. https://www.daido-life.co.jp/sustainability/management/practiceguide.html
出典:“インパクトを生むサステナビリティレポートの作り方”. zevero.earth. 2025-02-12. https://www.zevero.earth/ja/blog/how-to-create-sustainability-report-that-drives-impact
売れるPOPの具定例として、下の画像をご覧ください。
見て!読んで!「視覚で引きつけるコピー訴求例」の参考に。
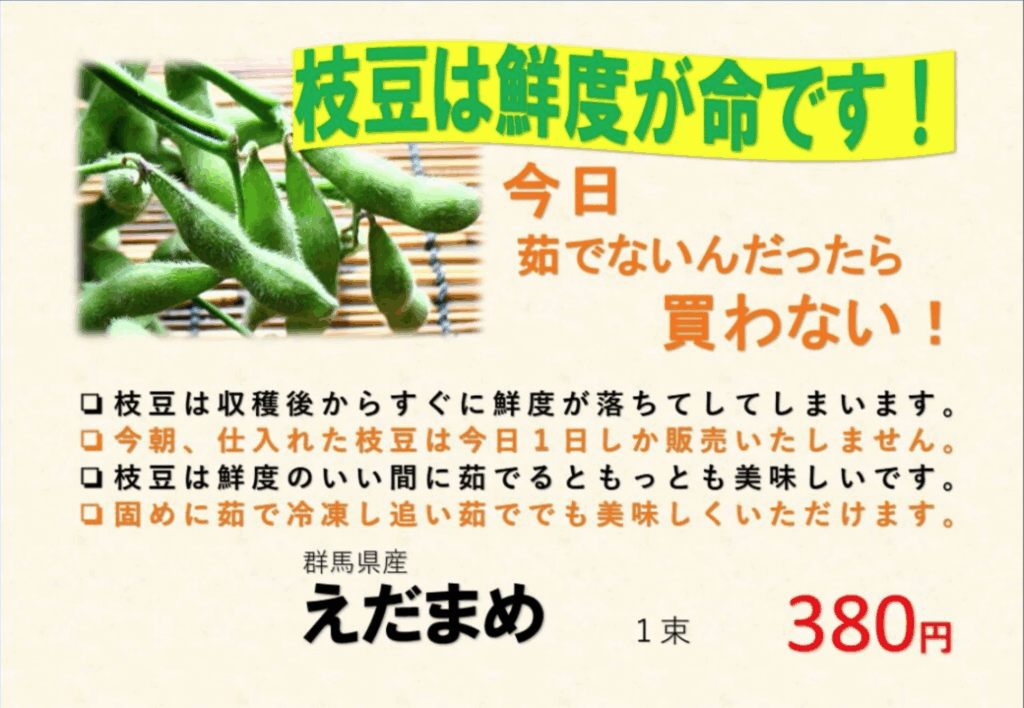
大企業との差別化につながる「小さなサステナブル」。
SNS・POP・パッケージで
“共感されるエコロジー”を見せる
中小事業者の強みは、小回りの利く対応と地域との密着です。
前述のコピー事例にも挙げたように
職人が作る一点物や、地域の伝統素材を活かした製品は、
その価値が伝わればブランド力につながるのです。
SNSでは製品の裏側や素材の背景を伝えるコピーと写真で、
顧客との距離を縮められます。
店頭ではPOPに素材や産地をしっかり記載するだけで信頼感も生まれます。
さらに、環境・社会課題を「自分ゴト」と感じさせることで、
サステナブルな消費は飛躍的に増えると言われています。
「自分ゴト」とそれ以外の(「決まりゴト」「学びゴト」)を比べると、
「自分ゴト」と捉えた人ほど購買につながる傾向があるのです。
つまり、異常気象や健康への影響などを具体的で身近な体験として
伝えることが有効な手段となるでしょう。
これにより、サスティナブルな課題が他人事ではなく、
自らの行動につながるメッセージに変換されるのです。
出典:“PwC Japanグループ.“サステナビリティに関する消費者調査 2024”. PwC Japan. 2024-07-02. https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/2024/consumer-survey-on-sustainability202407.html,
アクセス日:2025-08-15.
実践しやすい!導入例
「小さなサステナブル+エシカル消費」
最近は「エシカル消費」という考え方も広がっています。
エシカル消費とは人・社会・地域・環境に配慮した消費行動を指し、
地域の活性化やフェアトレード(*4)など、ただ安いだけでなく誰かを支える選び方
として広がっています。これは、人・社会・環境への配慮を意識して
商品やサービスを選択する消費行動のことです。
SNSやPOPでは、「この商品で〇〇さんを応援できます」といった
コピーを素材・ストーリーとともに発信することで、
消費者にとって「選ぶ一歩」が自分ゴトになります。
たとえば、以下のような取り組みは規模が小さくてもすぐに始められ、
SNS・POP・パッケージと連動させることで「共感されるブランド価値」を高められます。
(*4)フェアトレードとは=開発途上国の生産者と消費者を公正につなぐ仕組みのこと。
適正な価格で取引し、生産者の生活向上や自立を支え、環境にも配慮した持続可能な生産と消費を目指す
取り組みを指します。つまり「安さ優先の取引」ではなく、作り手の努力や地域社会を尊重する“公正な貿易”のこと。
実例としては、
1) 仕入れ段階からのエシカル選定
地域農家やフェアトレード業者からの直接仕入れをPOPやSNSで明示し、
「誰を支えている商品か」を可視化。
2) 製造工程の“見える化”
製造現場や職人のインタビューを動画や写真で発信。
消費者の安心感と関心を喚起。
3) 地域循環パッケージの採用
回収・再利用が可能な資材を導入し、
「この袋は〇回まで再利用できます」といったメッセージをいれる。
4) 購入による社会貢献を明示する
売上の一部を地域環境保全や福祉活動に寄付し、その活動報告を定期的に発信。
5) 購入長寿命デザインの推奨する
修理可能な商品や長く使える素材を採用し、
「長く愛される=資源の節約」を明確に訴求。
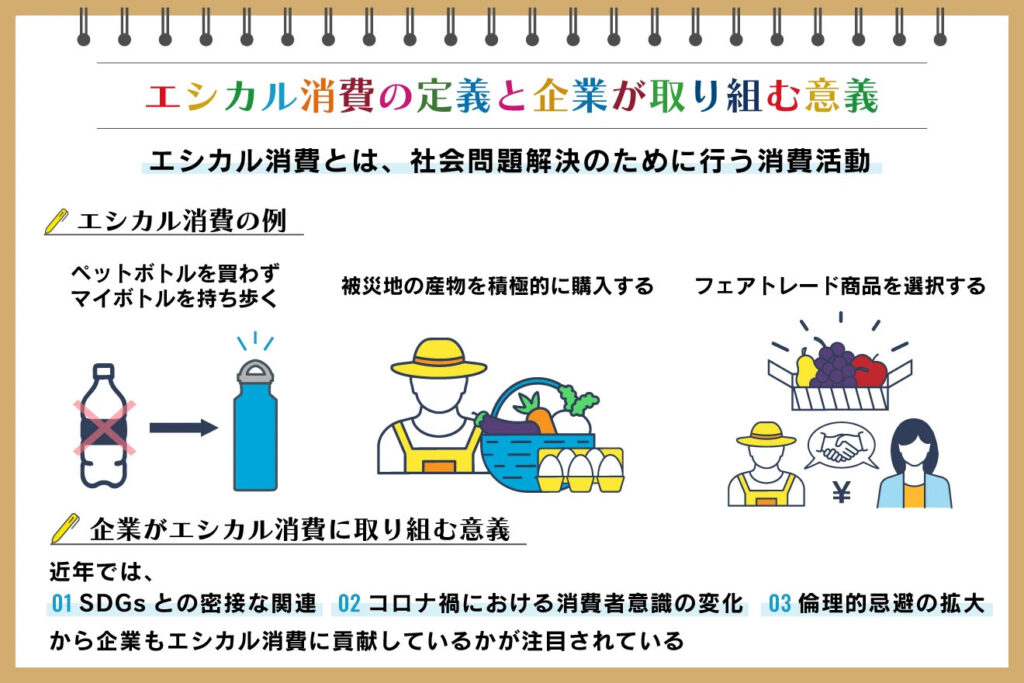 「エシカル消費」の定義と取り組みを視覚化した図。倫理的な消費を伝えるのにぴったり
「エシカル消費」の定義と取り組みを視覚化した図。倫理的な消費を伝えるのにぴったり
出典(画像):中小企業診断士/大橋信太郎,朝日新聞SDGsACTION,エシカル消費とは? 企業にとっての重要性や事例、取り組み方を解説,https://www.asahi.com/sdgs/article/14703483?utm_source=chatgpt.com, 2022-08-26.
中小事業者にとっては、このエシカル消費の価値観を発信に取り入れることで、
単なる商品の販売ではなく「社会貢献型ブランド」としての信頼を築くこともできるのです。
出典:消費者庁.“エシカル消費とは”. 消費者庁エシカル消費特設サイト.
https://www.ethical.caa.go.jp/ethical-consumption.html,アクセス日:2025-08-15.
出典:PwC Japanグループ.“サステナビリティに関する消費者調査 2024”. PwC Japan. 2024-07-02. https://www.pwc.com/jp/ja/press-room/2024/consumer-survey-on-sustainability202407.html, アクセス日:2025-08-15.
これらは、単なる環境配慮に留まらず、
「社会性+顧客との関係性+地域貢献」を兼ね備えた戦略として機能します。
結果として、大企業の大量生産・大量消費モデルとは異なる
「顔の見える価値提案」となり、価格競争からも一歩抜け出せます。
まとめ
サステナブルな取り組みは、小さくても意味があります。
大切なのは、自社らしい言葉と写真、そしてわかりやすい説明。
さらにカギになるのが、「自分ゴト」であることです。
「自分だったらどんな言葉や行動が響くか?」を考え、
自分目線の次に、奥さん目線、お子さん目線など、
さまざまな立場に置き換えて発信しましょう。
そこに、少しでも、人、社会、環境などに配慮した選択を行う、
「エシカル消費」の考えや理念を発信に少し組み込むことで
「社会貢献型の事業者」としての信頼や支持が期待できます。
目線を同じくし、顧客・地域・社員に共感してもらうことは、
大企業にはない「顔の見える心がふれあえる伝え方」です。
まずは自分ゴトの自分目線からはじめ、
その想いを継続的に発信していくことで、
持続可能なサステナブル経営とエシカルな姿勢が根付くに
違いありません。