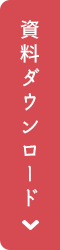第42回経営者コラム|トレンドについて考える10 メンタルヘルスへの意識向上! “整う”を大切にするZ世代に見る 人材不足と育成のポイント

「最近の若い者は…」だれしも一度は言われる言葉です。
いまの若い世代は「まず整える」「よく休む」を大切にします。
いっぽう50代以上は「最後までやり切る」が身についています。
どちらが正しいか?正しくないか?ではなく、
実は、フタを開ければ、整えてからやるか?やってから整えるか?の
順番の違いだけなのです。
今回コラムは、Z世代だけでなくあらゆる世代に役立つ
「心の回復」「言いやすい空気」「小休み」「身近な教え方」を、
そのまま真似できる手順でまとめました。
お互いの強みを合わせれば、働きやすく続けやすい職場になりやすくなりますので、
今日からできる小さな工夫で、人材育成と離職の予防に役立ててください。
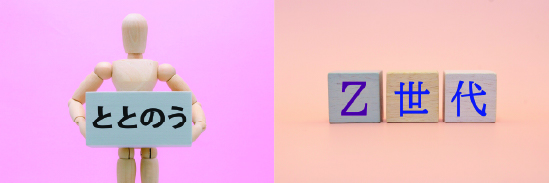
目次
まずは、少し変えてみる。
メンタルケアに対しての認識
小さな会社ほど、1人欠ける痛手は大きいですね。
だからこそ社員一人一人に対する
「整える=メンタルケア」の取り組みは、売上や安全の土台ともなります。
すぐできる実例として、やることはたった3つ。
1)匿名ミニ調査(月1回1分)
・体調0~5、気分0~5、現在の仕事の詰まり具合(一言)。
・個人は特定せず部署の傾向だけ共有。
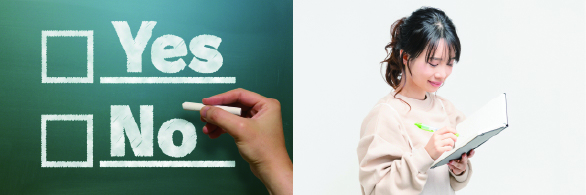
2)1on1(ワンオンワン) :上司と部下1対1の短い話し合いの時間
毎回同じ3つの問いと答えの形式で進める=毎月1回15分
・最近よかったこと/今いちばん詰まっていること
・詰まっていることを解決するにはどうする?次の一手(5~15分でできる行動)
・話し合いの冒頭30秒程度で、前回の一手の結果確認。

- 夜の重い連絡は翌朝へ:
・緊急以外は翌朝返信OKを一行ルールで掲示
・「休む=回復も仕事」と並べて明確に。
公的指針でも、事業者が計画・教育・環境改善・一次~三次予防を進める重要性が
示されています。まずは見える化→短い対話→一行ルール。
このような取り組みは、紙1枚で始められます。
【こんな時は/こうする】
社員の毎日の状況を把握する方法
例)朝礼時に今日の体調やメンタル状況をチェック
① 体調0~5を指で合図
② 0~1の人は午前を軽作業へ
③ 終わりに60秒呼吸(吸4秒・吐6秒×5回)
メンタルを整えることは福利厚生の一部ではなく、「生産性の土台」なのです。
認識をこのように変えることが、最も費用対効果の高い取り組み
と言えるかもしれません。
出典:厚生労働省.“労働者の心の健康の保持増進のための指針(あらまし)”. 厚生労働省, 2025-10-26, https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000153859.pdf, 改定:2015-11-30. 厚生労働省
出典:経済産業省.“健康経営オフィス レポート”. 経済産業省, 2025-10-26, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/downloadfiles/kenkokeieioffice_report.pdf, 作成:2016-03-31.
力が出ない?出社できない?
状態を見分けて手を打つ
社員がどんな状態にあるのか?見える化し原因に合わせた手を
こまめに打つのがキーポイントです。
では、まず知ろう!社員がどんな状況か?を示す言葉
「プレゼンティーズム」と「アブセンティーズム」とは?
「プレゼンティーズム」とは
=出勤しているが力が出ない状態
↓こんな状態が「プレゼンティーズム」
例)風邪気味で効率半分、強い不安でミス増、慢性的な睡眠不足で判断が遅い。
「アブセンティーズム」とは
=欠勤・遅刻・早退などでそもそも働けない状態。
↓こんな状態が「アブセンティーズム」
例)病欠・メンタルの長期休職・遅刻の増加。
現状を上司や管理者が共有し、その “兆し”を見逃さないことが大切。

見逃さないためにできることと
ストレス解消としてできることは?
◎見逃さないためにできること
・匿名ミニ調査
・1on1( ワンオンワン)
・勤怠の週次ダッシュボード(部署のみ記載し、匿名表示)
・繁忙週の事前ヘルプ枠を作る
◎ストレス解消として社員自身や周囲も巻き込んでやれること
・午前・午後の3分リセット(=伸び→深呼吸→目を閉じる)
・業務の多さを30分応援シフトで調整、周りが応援で手を貸す
・睡眠とセルフケア情報の配布
・有給の計画付与
官公庁資料でも、環境整備と健康行動の改善が、
「プレゼンティーズム」と「アブセンティーズム」の低減につながることと、
その枠組みが示されています。大がかりな仕組みより、
状況の見える化→小さな調整→休みやすさが、調整のカギになります。
出典:厚生労働省 こころの耳.“プレゼンティーズム(用語解説)”. こころの耳, 2025-10-26, https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-3003/, 掲載日不詳. こころの耳
出典:厚生労働省 こころの耳.“アブセンティーズム(用語解説)”. こころの耳, 2025-10-26, https://kokoro.mhlw.go.jp/glossaries/word-3010/, 掲載日不詳. こころの耳
出典:経済産業省.“健康経営関連資料・データ(健康経営オフィスレポート案内)”. 経済産業省, 2025-10-26, https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei_data.html, 更新日不詳(PDF:2016-03-31).
“整える習慣”を育成に活かす。
「ノートに書き出す」「深呼吸」「睡眠」を整え作法として社員に共有してみよう
とくにZ世代は、ノートに感情を書き出す「ジャーナリング(*1)」、
「短い瞑想=深呼吸」、「睡眠の質向上」などを、
上手に取り入ていると言われます。
この自然な習慣を若手社員などの育成手段として組み込むのも良いでしょう。
(*1)ジャーナリングとは=頭の中をいったん紙に出して整理する短い書き出し習慣

「整え」を使った 3つの育成メニュー
1)3行ノート=(ジャーナリング)
事実/気持ち/次の一手を各1行で書き出してみる。
例えば、朝礼後3分、会議前1分などでOK。
2)瞑想=深呼吸(60~90秒)
椅子のまま、吸4秒→吐6秒×5回。クレーム対応の切り替えなどの特に役立つ。
3)睡眠について
終業2時間前から重い連絡を控え、急ぎ以外は翌朝返信。
“書くこと”は心の整理に役立つ可能性が示され、
公的な睡眠ガイドも具体策を示しています。
整えの積み重ねは、やがて良い大差になって行きます。
出典:厚生労働省.“健康づくりのための睡眠ガイド2023”. 厚生労働省,
2025-10-26, https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001181265.pdf, 改定:2023-12-21. 厚生労働省
出典:J-Net21(中小機構).“仕事のパフォーマンスと睡眠の関係性について教えてください。” J-Net21, 2025-10-26, https://j-net21.smrj.go.jp/qa/productivity/Q1481.html, 公開:2023-11-24.
“質問はするな見て覚えろ!”
“先輩の背中を見て学べ!”の考えは、少し脇に置いておこう
「見て覚えろ」は、ハードルが高い方法です。まずは、そのまま真似できる手順が鍵。
以下の3点が効果的だと言われています。
【育成設計のポイント!】
1)仕事をいくつかのステップに分解し、各ステップの合格基準を設ける
2)業務の練習は短い動画などが有効。s
学びを動画で“度々再生可能”にしておくと、新人や部署異動でも伝わりやすい
3)フィードバックは1~2分にとどめる。長い説教は記憶に残らない
良かった行動はすぐほめる、改善点は次回の「一手」まで落とし込むことがポイント
このように、「定型パターン=習慣」が、人を育てることに役立ちます。
もちろん、先輩の背中を見ることも学びが多いでしょう。
ただ、新人を育てる入口や異動部署で業務の場合、
決まった定型パターンを作れば先輩である上司も新人も、お互いが
スムーズに業務を遂行することができやすくなることも、忘れずに。
出典:Google re:Work チーム.“ガイド:『効果的なチームとは何か』を知る(Project Aristotle)”. Google re:Work, 2025-10-26, https://rework.withgoogle.com/intl/jp/guides/understanding-team-effectiveness, 掲載日不詳. Rework
出典:内閣府 経済社会総合研究所(ESRI) 戸田淳仁ほか.“OJTとOFF-JTの相乗効果に関する分析”. ESRI, 2025-10-26, https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/archive/bun/bun199/bun199d.pdf, 公開:2019-12-20. ESRI Japan
小さなルールから現場を変えて行くと、空気感もきっと変わる!

新人などに「何でも言ってね」の声かけだけでは不十分。
言いやすい現場や状況をを作り上げなくてはなりません。
話し方の順番と、責めない記録の型を決めると、
きちんと意見が出るようになります。
例)上司が部下に対し、会議で話しやすい状況を作るには?
「良いね→懸念な点→代案」の順に話を進める
例) 部下がミスした場合
感情を乗せて語らない。責任追及より再発防止に時間を使うのがポイント
ミスは「事実→原因→再発防止」のテンプレートに沿って共有することを心がけましょう
ルールを明確にする
例) 連絡時間の境界線を明確にする
緊急時以外は既読不要タイムを定め、端末の通知設定ガイドを配布
心理的な安心感(安全性)が高いほど発言は増え、社内の人間関係の摩耗が減ります。
国内研究でも、謙虚なリーダー→心理的安全性↑→本領発揮の関係が示されています。
まずは、小さな積み重ねを続け、空気感を変えましょう。
出典:東京大学 先端科学技術研究センター.“謙虚なリーダーのもとで心理的安全性が高まりメンバーが本領発揮しやすくなる”. 東京大学, 2025-10-26, https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0211_00056.html, 公開:2024-03-15. 東京大学
まとめ
「よく休み、整えてから動く」。
この当たり前を、会社の仕組みに据えてみませんか。
休むことを許せる組織は、走ることも上手です。
Z世代が得意とする“整える文化”は、決して特別なことではありません。
人が人らしく働くための、静かな強さであると考えます。
小さなルールの積み重ねで、明日の社内は変わります。
人材不足の時代だからこそ、メンタルを土台にした育成で、
「辞めない」・「育つ」・「選ばれる」会社へ。
今日から、ちょっとしたルールと習慣で始めてみませんか。